「折り紙」という言葉を探して読書しているわけではないのだが、またそれに遭遇した。堀江敏幸さんのエッセイ
『ブーゲンビリア補遺』(
『坂を見上げて』所収)内の一文で、ブーゲンビリアの描写である。
折り紙細工の筏(いかだ)のような輪郭の、いかにもたっぷりした花弁に見える部分は苞(ほう)と呼ばれ、小さい白い花を守る包みにすぎない。
「折り紙細工の筏のような輪郭」とはどういうものだろうか。ゆったりと読書にひたっていればよいのに、またも「折り紙警察発動」かと自分でもきまりが悪いのだが、どうしてもひっかかってしまう。筏といえば、線材が組まれたかたちを思い浮かべる。そして、輪郭はだいたい長方形だ。ブーゲンビリアの苞葉の輪郭は、太った涙滴のようなかたちで、葉脈のダンダラがとくに目立つということもなく、筏には似ていない。
もっとも、ここに筏がでてくる理由は想像がつく。花筏(はないかだ)の印象があって、それに文章がひっぱられたのだろう、ということだ。水面に漂う花びらのさまを表現する花筏ではなく、種名としてのハナイカダ、葉の上に花の咲く植物である。それは、ブーゲンビリアに似ているところがなくもない。じっさい、ブーゲンビリアの和名は、イカダカズラ(筏葛)という。
ハナイカダの葉も、そのかたち自体が筏に似ているわけではない。葉の上に花がちょこんと乗ったさまを、船底の低い小さな船の上の船頭に見立てたものだ。それは、自然の多様性の妙というか、想像では思いつかないかたちをしている。知識なく初めて見たひとは、虫こぶのような寄生や奇形と見るに違いない。ちなみに、東アジア産のハナイカダ科(*)ハナイカダ属だけではなく、地中海地域原産である別の科のルスカス(梛筏:ナギイカダ:これも和名は筏だ)も、同様に葉に花がつくので、このかたちはハナイカダの専売特許ではない。
(*注:ハナイカダ属は、ミズキ科に分類されていたが、ここ20年ほどの被子植物の分子系統学(APG体系:被子植物系統グループ体系)で、独立のハナイカダ科になった。ただし、以前の分類法は並行して残っている。『理科年表』もそうだ。『理科年表』には、植物分類表と動物分類表が隔年に掲載されており、2019年度が植物の年である。これはついさきごろ刊行され、「最新の文献に基づき、生物部『植物分類表』を全面改訂」と案内されていたので、どうなったのかと見ると、APG体系にはなっていないのであった)
正方形の一枚折りでハナイカダをつくってみたのが下の写真である。前例としては1997年の『季刊をる』8号の、津田良夫さんと石原宗典さんのものがある。ハナイカダの花弁の数は3または4、雌雄異株で雄花と雌花が別になり、花の数は雄花数輪、雌花1-2輪だということで、これは雌花をモデルにしたものになる。花の色は白とはいえないが、やはりインサイドアウト技法をつかいたくなる。
そして、ブーゲンビリアである。これは、ハナイカダと違って、苞葉と花がそれぞれ分離した葉柄と花柄の先についているので、それ自体を筏に見立てるのは難しい。イカダカズラという名は、ハナイカダあってこその「同類」としての名づけであろう。
筏に見えるかどうかは難しいが、大きな苞葉の目立つ、たとえばハンカチノキのような「花」が、紙細工のように見えることは間違いない。満開のハンカチノキの実物をみたときは、まるで袋掛けをした果樹のようで、自然のものには思えなかった。ブーゲンビリアに関しても、南国の女性の髪飾りになる大輪の花という漠然とした印象を持っているだけだったが、写真を見ると、ふわふわした紙に包まれた小さな花で、全体として造花のように見える。その意味で堀江さんの比喩はぴったりだ。
と、連想が連想を呼んでとりとめなくなっているが、堀江敏幸さんのこのエッセイでは、以下の部分も、ディテイルが知りたくなった。
ブーゲンビリアは、十八世紀フランスの冒険家で、『世界周航記』を書いたルイ=アントワーヌ・ド・ブーガンヴィルの名にちなんだものである。一七六六年の暮れ、彼は博物学者ひとり、画家ひとり、天文学者ひとりを引きつれて三本マストの快速軍艦に乗り込み、積荷専用の船を一隻したがえてブルターニュ地方の港ブレストから南米に向かった。
ブーゲンビリアの名前の由来もブーガンヴィルというひとも知らず、18世紀フランスの海洋進出事情の知識もなかったが、気になったのは、探検船に同乗した天文学者は誰かということだ。これは、
フランス語版のwikipediaに情報があって、ピエール=アントワーヌ・ヴェロンなるひとであった(英語版と情報が違っていたが、フランス語版が正しいだろう)。ヴェロンは、天文の事典等には情報はないひとだったが、ジェローム・ラランドの教え子だということがわかった。
『ラランデ暦書管見』(1803ごろ)のラランドである! などとエクスクラメーションマークをつけても、「おお」と思うひとはそう多くないだろうが、和算史や天文史に興味がある者には、かなりの重要人物である。幕府天文方の高橋至時が、ラランドの著書
『天文学』(1764)のオランダ語訳を入手し、その注解書をのこしている。それが
『ラランデ暦書管見』で、本邦の天文学や暦学においてエポックとなる業績のひとつなのである。ヴェロンと高橋は、大洋を隔てたお互いを知らない兄弟弟子であった、と言えなくもない。ヴェロンは、太平洋の大きさを測ったひととして知られるらしいが、高橋の弟子である伊能忠敬が正確な日本地図をつくったというのも興味深い。
驚いたのは、ブーガンヴィルが、20代半ばで『積分論』(1754)という本を書いていて、数学者の側面も持ったひとでもあったことだ。18世紀の天文学者ヴェロンもまた数学者でもあったはずなので、測量などの議論の相手になったのだろう。そして、wikipediaの受け売りだが、面白い話はほかにもあった。世界周航に同行した博物学者・フィリベール・コメルソン、彼はまさにブーゲンビリアの名づけ親なのだが、その助手にジーン・バレというひとがいて、その本名がジャンヌ・バレであったという話だ。ジャンヌ、女性名だ。つまりジャンヌは、女性であることを偽ってこの船に乗船したのだ。そして、世界一周をした初めての女性となった。
なお、堀江さんのエッセイのタイトルが『ブーゲンビリア補遺』となっているのは、エッセイ中にも説明があるが、ブーガンヴィルの『世界周航記』(1771)に材をとった、ドゥニ・ディドロの、西洋文明を相対化する視点の創作『ブーガンヴィル航海記補遺』(1772)という書物があることに基づく。
ディドロといえば、拙著『本格折り紙√2』に、ディドロの『盲人書簡』に載っている立方体の六等分の話を引用したことを思い出す。いま思うと、あれは唐突な引用だった。せめて、立体図を思い描くときに、目を瞑ったり遠くを見ることがある、という話を書き添えればよかった。もちろん紙に図を描くことも多いが、視覚情報を遮断して、立体を抽象的に思い描くことが、わたしにはよくある。あるいは、盲目の折り紙作家・加瀬三郎さんや葛原勾当のことを書いてもよかった。
かくして、連想があぶくのようにわきあがり、はじけていく。









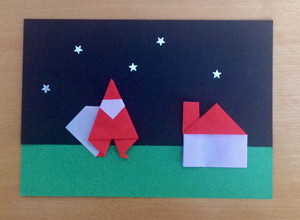










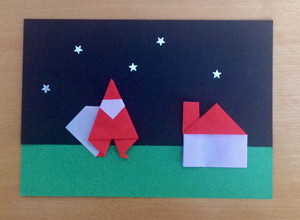

最近のコメント