開始 ― 2007/07/06 12:49
ドーキンス氏の折り紙 ― 2007/07/06 12:58
話のポイントは、折り紙(具体的には「中国のジャンク」というモデル)が、単純な手順の逐次的な積み重ねで成り立っていて、情報としてデジタル化されており、しかも、その手順に「自己正常化」が組み込まれているということである。ミームを説明する文脈に沿った例として、まさにぴったりである。
しかし、折り紙者としては、注釈を付け加えたくなることもあった。折り紙造形はつねに順序の決まった手順によってつくられるのではない、ということである。じっさい、折り紙の手順は入れ換えも可能である。手順をまったく意に介さないことさえある。たとえば、折り紙創作家には、次のようなひとも多いはずだ。
自分が創作した作品はいつでも折ることができるが、その手順は覚えておらず、というか、考えてもおらず、展開図(作品を展げたときについている折り目)という全体構造で覚えている、というひとだ。まあ、そうした作品は、そもそもミームの例になりにくいけれど。
伝承作品においても、それが淘汰を経て伝わっている理由は、手順の明快さにのみあるのではない。それは、(手順とも密接に関係するが)構造の明快さにもある。折り紙の情報伝達において、「自己正常化」がなされるのはなぜか。手順を誤った場合にそれを改めることが可能なのは、構造の明快さというゴールがはっきりしていて、それぞれの手順がそうした構造に奉仕するものとなっているから、でもある。
時間という名の解(ほど)けない折り紙 ― 2007/07/08 19:12
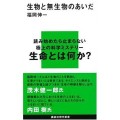
そこでは、非可逆的で自己修復性のある生物の発生・成長のプロセスの比喩として、「ほどけない折り紙」なる表現が使われている。非可逆、自己修復性のほか、部分への分割が難しいことも強調されている。
細かいことにこだわるようだが、この比喩には、若干の違和感もあった。
折り紙における折るという変形(少なくとも数学的に抽象化したもの)は、可逆であると見なせることに本質がある、とも言えるからである。「折るとは、つまり、破かず、切らず、伸び縮みさせないことである」といった表現をすれば、可逆の意味がわかってもらえるのではないだろうか。
ただ、この本の「折り紙」は「ほどけない折り紙」であり、そもそもが修辞的な表現なので、ちょっとした違和感であるにすぎない。
それよりもわたしは、著者がなぜ折り紙という比喩を使ったのかということに思いを巡らした。
折り紙と生物の形態形成の類似性は、これまでも、本多久夫さんなどにより語られている。しかしそれは、『生物と無生物のあいだ』の主テーマである「動的平衡」とは異なる観点である。本多さんが指摘しているのは、生物のシート構造と折り紙造形の類似性である。つまり、生物の構造は、かたまりではなく、うねったシートによってかたちづくられているということである。
このシート構造というイメージを、「折りたたんだものをさらに折りたたむことは、それまでに形成されたものを内包してゆくことである」というふうに解釈すると、本書の比喩にもつながる、と言えなくもない。
しかし、非可逆的な動的平衡による形態形成ならば、たとえば、台風のような気象現象との類比のほうが、より相応しいのではないか、という思いは捨て切れない。それなのに、著者は、なぜ折り紙という比喩を使ったのだろうか。
これは案外、折り紙が喚起する詩的なイメージが気にいったということだけなのかもしれない、とも思う。
難民キャンプの折り紙 ― 2007/07/09 12:51

著者には、クロアチアの難民キャンプでボランティア活動をしたことがあるアイルランド人の友人がいる。エッセイの内容は、その友人(女性)が、日本のボランティアグループが流行らせたオリガミのために、「オリガミができなければ先生はとてもつとまらないということを、初日で思い知る」という話である。彼女にとって、遠い東洋の一国・日本の印象は、まず折り紙から始まった、というような話だ。
題名は「折りに触れて」のダジャレである。なお、細かい言葉遊びも含めて、著者の日本語はおどろくほど達者だが、ひとつ「的を得た」という表現があった。「的を射た」か「当を得た」である。著者というより、編集者さん・校正さんの見落としだなあ。(11年後の追記 2018/1/7 「的を得る」は誤用とは言えない(誤用としていた、三省堂国語辞典』第7版に「的を得る」が載った)という話を聞いた。ビナードさん、編集者さん、ごめんなさい)
「車」という文字のわずかな対称性の乱れを明らかにする物件 ― 2007/07/10 12:32

マンガ史上に輝く史跡 ― 2007/07/10 12:40

まずは、『ゲゲゲの鬼太郎』のねこ娘の住み処だ。『鬼太郎』の一エピソード・『ねこ娘とねずみ男』に記述された「調布の中華そば屋の隣りの神社の下」の神社とは、この神社のこと(八幡神社 調布市富士見町)なのである。なお、わたしが訪ねたときは、ねこ娘も猫もいなかった。
そして、この中華そば屋こそが、つげ義春氏が「ラーメン屋の屋根の上で見た夢」と語った、あの『ねじ式』が生まれた場所なのである。
このような聖地が自宅から徒歩20分のところにあるのは、たいへん誇らしい。
ちなみに、わたしは、水木先生に一度だけ会ったことがある。3年前の「妖怪折り紙コンテスト」審査のときの役得である。舞い上がって、ツーショットの写真を撮ってもらうのを忘れて後悔していると、同道した西川誠司さんに「こんなにハイになっている前川さんは珍しい」と言われた。
折り紙関連(?)で言えば、このとき、わたしは、かねてより疑問に思っていたことを訊いてみた。
「おりたたみ入道という妖怪は、伝承や出典があるものですか。水木先生の考えたものですか」
アシスタントさんは即答した。「水木の考えたものです」
どこかに伝承があれば、詳細に調査して『折紙散歩』(『折紙探偵団マガジン』連載中)のネタにしようと思っていたのに。











最近のコメント