時間という名の解(ほど)けない折り紙 ― 2007/07/08 19:12
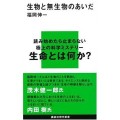
そこでは、非可逆的で自己修復性のある生物の発生・成長のプロセスの比喩として、「ほどけない折り紙」なる表現が使われている。非可逆、自己修復性のほか、部分への分割が難しいことも強調されている。
細かいことにこだわるようだが、この比喩には、若干の違和感もあった。
折り紙における折るという変形(少なくとも数学的に抽象化したもの)は、可逆であると見なせることに本質がある、とも言えるからである。「折るとは、つまり、破かず、切らず、伸び縮みさせないことである」といった表現をすれば、可逆の意味がわかってもらえるのではないだろうか。
ただ、この本の「折り紙」は「ほどけない折り紙」であり、そもそもが修辞的な表現なので、ちょっとした違和感であるにすぎない。
それよりもわたしは、著者がなぜ折り紙という比喩を使ったのかということに思いを巡らした。
折り紙と生物の形態形成の類似性は、これまでも、本多久夫さんなどにより語られている。しかしそれは、『生物と無生物のあいだ』の主テーマである「動的平衡」とは異なる観点である。本多さんが指摘しているのは、生物のシート構造と折り紙造形の類似性である。つまり、生物の構造は、かたまりではなく、うねったシートによってかたちづくられているということである。
このシート構造というイメージを、「折りたたんだものをさらに折りたたむことは、それまでに形成されたものを内包してゆくことである」というふうに解釈すると、本書の比喩にもつながる、と言えなくもない。
しかし、非可逆的な動的平衡による形態形成ならば、たとえば、台風のような気象現象との類比のほうが、より相応しいのではないか、という思いは捨て切れない。それなのに、著者は、なぜ折り紙という比喩を使ったのだろうか。
これは案外、折り紙が喚起する詩的なイメージが気にいったということだけなのかもしれない、とも思う。
コメント
_ Joker ― 2008/10/26 22:09
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://origami.asablo.jp/blog/2007/07/08/1636782/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。











動的平衡については、宮沢賢治の「わたくしという現象」という言い方を思い出しました。著者自身の経験から中心テーマに据えられていましたが、読者としては、少しはぐらかされたような気分。生命への畏敬は重要だと思うのですが、科学の方法を問い直すには、材料が微妙すぎる気がします。大根を正宗で切っているような。前半の比喩の切れ味が冴えていただけに、もったいない気がしました。とはいえ、私はこの本から、研究者が研究対象に抱く情熱をこそ学ばなければならないのかもしれません。
最終章に至ってこちらのブログの記述を思い出したのですが、もう一年以上前の記事だったのですね。なんとのんきな私であることか。