折紙工学に関する調査研究分科会 ― 2009/05/30 11:04
講演者と演題は、趙希禄さん(東京工業大学 特別研究員)「反転螺旋型円筒折紙構造- 大きく伸びたエネルギー吸収量」、五島庸さん(城山工業)「トラスコアパネル実用化のための生産技術開発」、川村みゆきさん(折紙作家)「やわらかユニット」、川口健一さん(東京大学)「膜構造と折り紙」というものだった。
どれもとても興味深かったが、趙さんのものをちょっと紹介。これは、この会のチェアマンでもある東京工業大学の萩原一郎さんが中心になって進めている研究の一環で、車のサイドメンバー(車の骨格で、進行方向に線状のもの)に、衝突時の衝撃吸収のために、きれいにつぶれる折り目をいれた柱状の構造物を使うというものである。趙さんの研究は、そこに五角形の構造を使うことで、エネルギー吸収量をあげることに成功したという内容だった。さらに多角形の辺の数をあげれば、吸収量はあがるのかもしれないが、「ピュタゴラス派」(?)としては、五角形というのが「おおっ」であった。
『天使と悪魔』とアンビグラム ― 2009/05/30 11:06
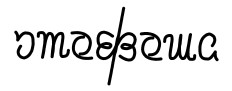
これは、『ダ・ヴィンチ コード』より面白いというか、よくできているのではないか。じっさいそんな声も多い。CERN(欧州原子核研究機構)の加速器の描写なども、反粒子の大量トラップを除けば(それが肝なのだけれど)、もっともらしいのじゃないだろうか。原作に、図像学的な蘊蓄が満載なのも想像できた。いまさらだけれど、読んでみよう。
反転させても読めるなどの対称性を持ったカリグラフィ(書のアート)・アンビグラムが重要な小道具になっているのも、にくい演出だった。名著『ゲーデル エッシャー バッハ』(R. ホフスタッター著 野崎昭弘、はやしはじめ、柳瀬尚紀 訳)で知られるようになったものである。まったく気がつかなかったが、主人公の図像学者・ラングドンの名もアンビグラフィスト(というのかな?)のジョン・ラングドンさんの名前からとったものだという。
図は、『ゲーデル エッシャー バッハ』を読んだときにつくった、わたしのアンビグラム的署名。「J MAEKAWA」と読めるよね。
『日本物理学会誌』伏見先生追悼特集 ― 2009/05/30 11:15
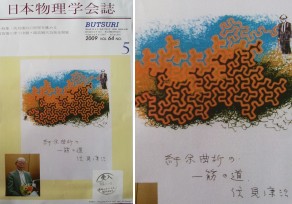
手を使うと頭がよくなるというが、伏見さんはその典型であったのかもしれない。図形や折り紙に関して次つぎと新しい定理を発見し、この世界が思いがけないほど広大であることを示した。この発見は伏見さんご自身にとっても驚きであったかもしれない。











最近のコメント